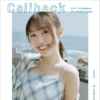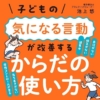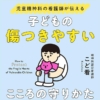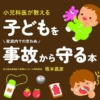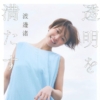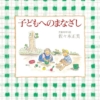「日の丸半導体」復活への希望か、それとも新たな依存の始まりか? 熊本に巨大工場がもたらす光と影。経済効果、環境破壊、そして歪む地域社会。TSMC誘致の真実を徹底追跡した、衝撃のドキュメント。

2021年、世界を驚かせたニュースが日本を駆け巡りました。世界最大の半導体受託生産企業であるTSMCが、熊本県に巨大な工場を建設するという発表です。「日の丸半導体」の復活、経済の活性化、雇用の創出──多くの人々が、このプロジェクトに希望を抱きました。メディアは連日、その経済効果を喧伝し、国も莫大な補助金を投じました。しかし、その華々しい光の裏側で、見過ごされてきた「影」があることを、私たちは知るべきです。
この一冊『光と影のTSMC誘致』は、私たちが聞かされてきた"成功物語"だけではない、もう一つの真実を徹底的に追跡した、渾身のルポルタージュです。著者は、熊本の現地に何度も足を運び、工場建設の現場、そしてそこで生活する人々の声に耳を傾けました。表向きには語られることのない、地域社会が直面する生々しい現実を、丹念な取材を通して浮き彫りにしていきます。
本書の最大の魅力は、多角的な視点から「光と影」を対比させている点にあります。
まず、「光」の部分。TSMC工場が熊本にもたらす経済効果は、確かに無視できません。関連企業が集積し、地価は高騰、雇用は増え、地元経済は活気づいています。これは、長年停滞していた地方経済にとって、まさに起爆剤と言えるでしょう。しかし、その一方で「影」の部分も明確に存在します。
一つ目の影は、「環境問題」です。半導体工場は、大量の水を消費します。日本の食糧庫である熊本の豊かな地下水が、工場の稼働によって枯渇するのではないかという懸念は、地元住民の間で深刻な問題となっています。水資源の枯渇は、農業や観光業といった、地域の基盤産業を根底から揺るがしかねない危機です。本書は、データと専門家の証言を基に、この水問題がどれほど深刻なものであるかを明らかにします。
二つ目の影は、「地域社会の歪み」です。TSMCの進出により、工場の周辺では土地の買い占めが横行し、地価は暴騰しました。これにより、長年その土地で暮らしてきた人々が立ち退きを余儀なくされるケースも出てきています。また、台湾からの技術者やその家族が大量に移住することで、言語や文化の違いによる軋轢が生じ、コミュニティのあり方が変わりつつあります。本書は、こうした人々の生の声を通して、見えないひずみが広がる様子を描写しています。
三つ目の影は、「日本の自立性」です。国が巨額の補助金を投じて誘致したTSMC工場は、果たして「日の丸半導体」の復活と言えるのでしょうか? 著者は、日本の半導体産業が、海外の巨大企業に依存する構造を強めているに過ぎないのではないか、という鋭い問いを投げかけます。技術のブラックボックス化や、米中対立の地政学的リスクに巻き込まれる可能性など、長期的な視点から見た日本の半導体戦略の危うさを指摘しています。
『光と影のTSMC誘致』は、単なる賛否両論を並べたものではありません。私たちは、国やメディアが作り上げた物語の向こう側にある、現実を知る必要があります。この本は、そのための羅針盤となるでしょう。熊本で今、何が起きているのか。その問題は、日本の未来にどうつながっていくのか。この一冊を読み終えた時、あなたはきっと、この国の未来を、自らの頭で考えるようになるはずです。