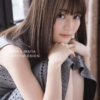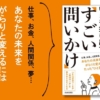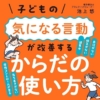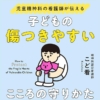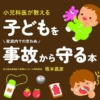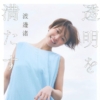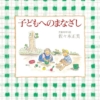「書くこと」の本質を探求する旅へ。言葉を「再履修」し、思考を深めるための哲学書。内田樹氏が解き明かす、書く行為の奥深さと現代社会への警鐘。
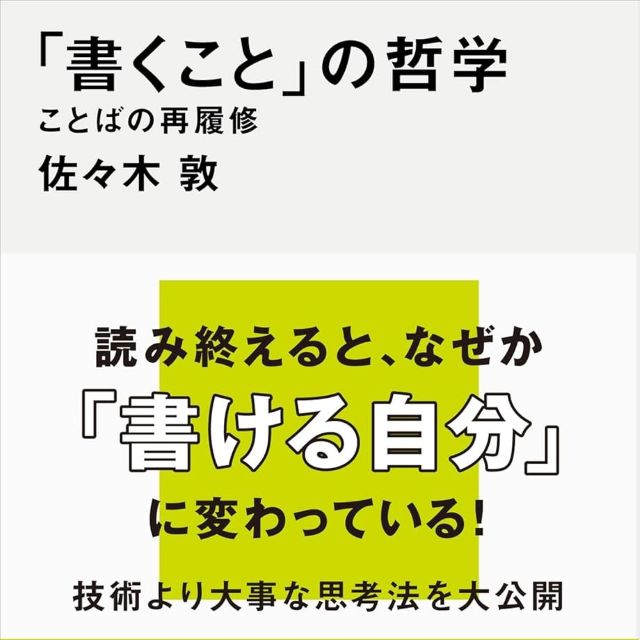
デジタル化が進み、誰もが気軽に「書く」ことができるようになった現代において、真に「書く」とはどういうことなのか。SNSの短文から論文、小説に至るまで、多様な形式で言葉を紡ぐ私たちにとって、書く行為の持つ意味や、それが私たちの思考に与える影響について深く考える機会は少ないかもしれません。そんな現代に一石を投じるのが、思想家・武道家として多方面で活躍する内田樹氏の著書『「書くこと」の哲学 ことばの再履修』(講談社現代新書)です。
この本は、単なる文章術の指南書ではありません。書くという行為を通じて、私たちは何を考え、何を感じ、どのように世界と関わっていくのか――その根源的な問いに向き合うための「哲学書」であり、まさに「ことばの再履修」を促す一冊なのです。
内田樹氏がこの本で繰り返し語るのは、「書くこと」がいかに私たちの思考と密接に結びついているか、そして現代社会においてそのつながりが希薄になりつつあることへの警鐘です。私たちは、ともすればSNSの「いいね」や、検索エンジンの上位表示を意識して、表面的な言葉を羅列しがちです。しかし、本当に「書く」とは、自分の内側にある曖昧なものを具体的な言葉として外界に提示し、それによって自分自身の思考を明確化していくプロセスであると内田氏は指摘します。書くことは、いわば「思考の外部化」であり、それによって初めて私たちは自分自身を客観視し、深めることができるというのです。
現代社会では、情報過多の時代ゆえに、私たちは「分かったつもり」になりがちです。ネットで検索すればすぐに答えが見つかり、多様な意見が飛び交う中で、自ら深く考察し、自分の言葉で表現する機会はむしろ減っているのかもしれません。内田氏は、こうした状況を「ことばの劣化」として捉え、もう一度、言葉と真摯に向き合い、その使い方を「再履修」する必要性を訴えます。それは、単に語彙を増やすことや文法を正しく使うことにとどまらず、言葉の持つ奥行きや多義性を理解し、それを操ることで思考を深める力を養うことを意味します。
本書では、具体的な文章の書き方にとどまらず、「書くこと」が私たちにもたらす内面的な変化や、知的活動としての意義についても深く掘り下げられています。例えば、書くことで私たちは、自分の中に眠っていた新たな感情や考えを発見することがあります。また、他者に向けて書く行為は、相手の反応を想像し、言葉を選ぶという「想像力」を鍛えることにもつながります。これは、現代社会においてますます重要性が高まる「共感力」や「対話力」の基盤を築くことにもなるでしょう。
さらに、内田氏ならではの豊富な読書量と、古今東西の思想家や文学者、哲学者の知見が引用され、単調になりがちなテーマに奥行きと広がりを与えています。読者は、プラトンからデカルト、そして現代の哲学者まで、様々な視点から「書くこと」の意味を問い直す機会を得られるでしょう。内田氏の独特の語り口と、時にユーモアを交えながら本質を突く論理展開は、読者を飽きさせません。難解な哲学用語を並べることなく、日常の具体例を挙げながら、読者が自分自身の体験と結びつけて考えられるように導いてくれるのも、本書の魅力です。
この本は、これから論文を書く学生はもちろん、ビジネス文書を作成する社会人、そしてSNSで日々発信を行うすべての人々にとって、「自分の言葉」を見つめ直すための羅針盤となるでしょう。書くことの苦しさや難しさに直面している人にとっては、その本質的な意味を理解することで、新たな視点とモチベーションを与えてくれるかもしれません。
『「書くこと」の哲学 ことばの再履修』は、情報過多の時代に生きる私たちが、どのようにすれば「考える力」を失わずにいられるか、そして「書くこと」を通じていかに自己を確立し、世界と豊かに関わっていくかについて、示唆に富んだヒントを与えてくれます。価格は、講談社現代新書ということもあり、900円台(税別)と手に取りやすい設定です。
ぜひこの機会に、本書を手に取り、内田樹氏と共に「書くこと」の奥深い哲学を探求し、あなた自身の「ことば」を再履修してみてはいかがでしょうか。きっと、これまでとは違う視点から、書くこと、そして思考することの喜びを発見できるはずです。