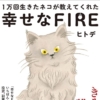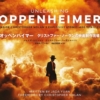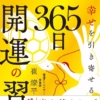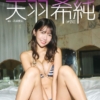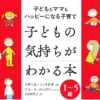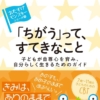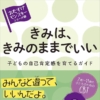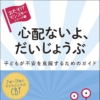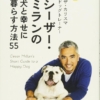「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策 「HRアワード2024」書籍部門・優秀賞受賞!コミュニケーションの課題を認知科学の視点で明晰に解説した書籍として多くの経営者や人事から高く評価
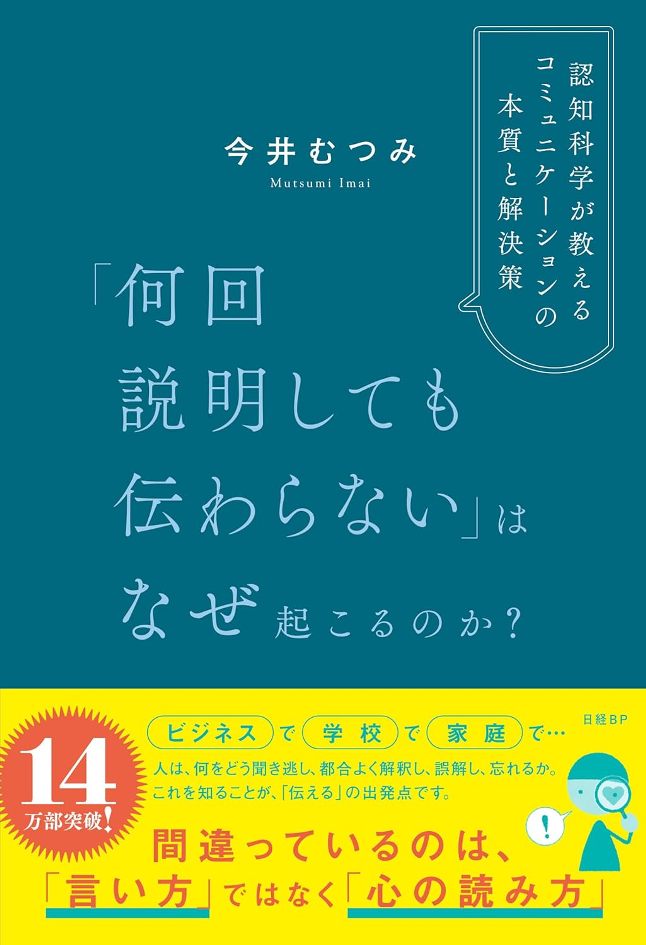
かつて、とある町に、情報の迷宮「コグニタ・タウン」がありました。そこでは、人々が日々の会話や議論を通じて知識を深め、成長することが大切にされていました。しかし、あるとき、住民の中で「何回説明しても伝わらない」と嘆く者が現れました。
迷宮の中の混乱
主人公のタカシは、町のプロジェクトチームでリーダーを務めていました。彼は新しいアイデアを何度もメンバーに説明しましたが、いつも「理解できない」と返ってくるのです。タカシは困惑し、どうして自分の言葉が届かないのか、心から悩んでいました。
そんなとき、町に住む賢者ユウキがタカシの元を訪れました。ユウキは、長い人生と多くの経験から、認知科学という知恵を学んでおり、こう告げました。
「タカシ、君の言葉が伝わらないのは、君が説明する『内容』と、聞く人たちが持つ『心の中の地図』が一致していないからなんだ。人はそれぞれ違う経験や知識を持っている。つまり、君が何回説明しても、相手の中にある『既存の枠組み』と合致しなければ、真意は伝わらないんだよ。」
認知科学が解く秘密
ユウキはさらに、こう説明しました。
・情報処理の限界
私たちの脳は、一度に処理できる情報に限界があり、複雑な話や新しい概念は一度の説明だけでは理解しきれない。
・既存の知識とのギャップ
相手が既に持っている知識や経験(=メンタルモデル)と、君の説明がズレていると、たとえ繰り返してもそのギャップは埋まらない。
・注意の偏りと認知バイアス
人は、自分の信じたい情報や、慣れ親しんだパターンに固執しがち。新しい視点や説明は、最初から否定的に受け取られることもある。
ユウキは、これらを「認知科学の真髄」と呼び、具体的な解決策も伝えました。
解決への道しるべ
共通の土台を作る
まずは、相手がどのような知識や経験を持っているかを理解し、共通の基盤を築くことが大切だ。
具体例や比喩を使う
抽象的な概念は、具体例や物語に置き換えることで、相手の心に響きやすくなる。
対話を通じた確認
一方的に説明するだけでなく、質問や意見交換を重ねることで、相手の理解度をチェックしながら進める。
情報の整理と分割
一度に多くの情報を詰め込まず、ポイントごとに区切って説明することで、脳の処理負担を減らす。
未来へ続く会話
タカシはユウキのアドバイスに耳を傾け、次の日からプロジェクトの会議で、まずメンバー一人ひとりの背景や知識を確認することから始めました。そして、彼は自分のアイデアを具体的な例え話や図解を交えて、ゆっくりと説明するようになりました。すると、不思議なことに、メンバーたちは次第にタカシの意図を理解し、積極的に意見を交わすようになったのです。
この物語は、「何回説明しても伝わらない」という悩みが、実は認知の仕組みや情報処理の限界から生じるものであり、適切な工夫によって必ず解決できるということを教えてくれます。ユウキの知恵は、タカシだけでなく、コグニタ・タウンのすべての住民にとって、より良いコミュニケーションの未来への道しるべとなったのでした。